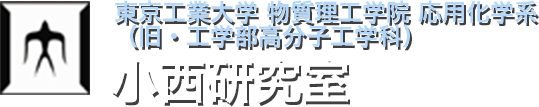小西玄一 准教授
略歴
1971年 リヨンに生まれ、NY州を経て来日
1990年 愛知県立岡崎高等学校卒業
1995年 大阪府立大学工学部応用化学科卒業(高田十志和教授、水野一彦助教授)
1997年 大阪府立大学大学院工学研究科物質系専攻修了(水野一彦教授)
2000年 京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻博士後期課程修了(中條善樹教授)
博士(工学)京都大学 取得
2000年 信州大学医学部医学科生理学教室 助手
2002年 金沢大学工学部物質化学工学科 助手
2006年 東京工業大学大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻 助教授
2007年 同 准教授(名称変更)
2012年 科学技術振興機構さきがけ研究員(新物質科学と元素戦略 細野秀雄統括)兼任
2016年 物質理工学院応用化学系 准教授
2020年 Associate Editor of "Aggregate" Wiley
(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26924560)
化学反応への拘り
卒業研究は、有機光化学の反応開発でした。その時の経験が、最初に見たものを親と思う動物行動学の「刷り込み(imprinting)」のごとく、今でも自分のアイデンティティーになっています。機能材料を開発する時も、綿密にデザインされた研究ではなく、少しナイーブなアイディアで何が起こるかわからない方を好みます。
最近は、発光材料をよく扱いますが、研究をやっていくうちに、結局、発光現象も化学反応だと感じるようになりました。福井謙一先生の「学問の創造(1982年)」の一節を載せます。
『この化学反応の経路に関する理論(Intrinsic Reaction Coordinate (IRC))によれば、化学反応にともなう分子の形の変化が自動的に計算される。それに従来のフロンティア軌道理論を加えることによって化学反応がまさしく映画のように、視覚的に表現し得る可能性が生じたのである。』
化学を職業に選択する前に読んだ本で印象的だった一節ですが、この話が、蛍光色素の研究に生きています。諸熊奎治先生と2016年に出した論文はまさにそれです。
ここに1970年代のボストンの物理学会(?)の写真があります。この中に、諸熊先生(左端)、福井先生(左から2人目)と髪の毛ボサボサの私が映っています。何か深い縁を感じます。

受賞
日本化学会第18回若い世代の特別講演会 2004年
第29回合成樹脂工業協会研究奨励賞 2005年
平成17年度高分子研究奨励賞(高分子学会)2006年
平成19年度東工大挑戦的研究賞 2007年
有機合成化学協会研究企画賞 2010年
光化学協会賞 2020年
有機合成化学協会・富士フイルム機能性化学材料賞 2023年
東工大教育賞(優秀賞・共同受賞・分担者) 2020年
東工大教育賞(最優秀賞・単独受賞) 2022年
など
大型研究プロジェクト代表者
2004年 産業技術研究助成事業 代表者
2005年 JST独創的シーズ展開事業・権利化試験 代表者
2007年 産業技術研究助成事業継続研究 代表者
2011年 産業技術研究助成事業 代表者
2012年 JSTさきがけ研究代表者